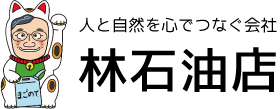「林石油店と5人のお客さま」第5回 助手席

「キーイ」と大きなブレーキ鳴きの音がして、ガソリンスタンドのエントランス・スペースに、見慣れた白いレトロな外国車が入ってきた。
「いらっしゃいませー」
いつもなら車を給油レーンに誘導するのが店員のひろしの仕事なのだが、この車が入車した時はそうはしない。ひろしの目の前を車は通り過ぎ、いつものように点検ピット前に停まった。
「なおきちゃん、いる?」車から降りてきた男が聞いた。
「いらっしゃいませ。今日、社長は、なんか木のベンチを軽トラに積んで、朝一番から出かけて行きました」
「ベンチ? ふーん」
そう言って、男は店内に入ろうとしかけたが、急に車の方に戻っていった。ひろしが視線をそちらに向けると、珍しく連れの女性が助手席に乗っているのが見えた。白いワンピースに、白い帽子をかぶった、上品そうな女性だ。
「マチ子、ブラックでいいか?」
そう聞かれた女性が軽く頷づくのを見て、男はいつもそうするように店内のカフェ・スペースに向かっていった。
「なおきがまたなんか始めたんか?」男は2人分のコーヒー・チケットをちぎりながら、店員の山下に聞いている。
「このあたりの野岡町でも人口減少と高齢化が進んで、昔は40軒あったお店も今では10軒ほどになったらしいです。2017年に店長は、今も残る10件のお店の軒先をお借りして、木のベンチを設置するプロジェクトを仲間の方々と始めたんです」
「へえ」次いで男は、コーヒー・マシーンの方に取り掛かっている。
「出歩くのが億劫になりがちなお年寄りも、座って話したくなる場所を作るというのが目的らしいです。冬の間、ベンチをうちで預かってたんですが、そろそろ気候も良くなったんで、今日はまたそれを設置しに行ったみたいです」
「まあ確かに俺がガキの頃は、お店の土間に丸椅子かなんかが必ずあったなあ。親におつかいとか言いつけられてそこに行くと、近所の年寄りやおばちゃん連中が必ず長話してた。井戸端会議、いや店先会議かなあ」
「そうなんです。その店先会議を復活させるため、社長が考えたのが木のベンチの設置なんですわ」
「なるほどな。と言っても『あそこの息子に嫁がくるだの。橋向かいのじいさん最近ボケなはったんや』とか、実際まあ大したことない噂話ばっかり」
「でもまあそれが、今で言う《地域内の情報の共有》になってたんでしょうね」
「にいちゃん。アレやアレ。今の若者が使うスマホにあるやろ。そういうの」ブラック・コーヒーの入った紙コップを2つ手にした男は、入り口近くに歩み寄り、黙って話を聞いていたひろしの方を見た。「マインとか、ナインとかいうやつ」
「え? ラ、『LINE』ですかね。」慌ててひろしが答えると、
「ああにいちゃん、それやそれ。やっぱり最近の若いやつは頭いいな」男はそのままひろしの脇を通り抜け、車の方に向かっていった。
ひろしがこの店に来て、一年が経とうとしていた。この間、ひろしが自動車整備士の資格を持っていることを知っているお客さまも徐々に増えてきた。「タイヤまだ大丈夫かな」とか「このエンジンの音なんだけど・・・」と相談を持ちかけられることも多くなっている。どちらかと言えば技術者タイプの人間であるひろしも、最近では先輩方を見習い、「オイル見ときますか?」「空気圧大丈夫ですか?」などという営業めいた声掛けもできるようになってきた。
しかし、この白い外国車の男には、なぜか自分の方からは話しかけることができないである。悪い人ではないのはわかっているが、馬が合わないというか、会話のタイミングが取りにくいというか、苦手意識が拭えないでいるのだった。
実はひろしには、随分前から気になっていることがあった。それは男の車の大きなブレーキ鳴きの音だ。

男の方を見ると、「マチ子」と呼ぶ女性に、優しくコーヒーを進めている。
「ああ見えて、あの人、この辺りでは奥さん思いで有名らしいわよ」洗車場から戻ってきた先輩店員の恵が、ひろしの側に来てそっとささやいた。
「そうなんですか」
「奥さんは足が不自由で、それでいつもああやって病院や買い物に送って行ってあげてるの」
「なんか意外ですね」
「いらっしゃいませー」その時、新しいお客の車が入車してきて、いち早く恵が駆け出して行った。ひろしは一旦あとを追いかけたが、思い直して男の車の方に向かっていった。

「あのー、すみません」
「なんや、にいちゃん。チケットはちゃんと2枚切ったぞ」
「いえ、そういうことではなくてですね。あのー」
「なんや、早く言えま」
「まあまあ、あなた。そんな風に言ったら、この子も何にも言えないでしょう」その時、マチ子さんが優しく助手席から口添えをしてくれたおかげで、ひろしの決心は固まった。
「このお車のことですが、前々からブレーキに異音がするんです」
「そんなことは俺でもわかってる。昔から『《オイル漏れ》と《ブレーキ鳴き》は、外車持ちの勲章』って言われてるんや。新車でも良くあるで。大したことないって」
「いや、確かにそうかもしれません。でも、もしものことだってあります。ディスクブレーキのブレーキパッドは、年数が経つと必ず摩耗していきます。パッドが残り少なくなると、ウェアインジケーターという部品がディスクローターに触れてキーキーと音をたてます。これはドライバーにパッドの交換時期を気付かせるためでもあるんです」
「確かにこの車も年季入ってるからなあ」
「大事な奥様を助手席にお乗せする車です。お時間は取らせません。ぜひ一度、僕にブレーキを点検させてください!」
思わず大きな声が出たものだから、山下や恵が思わずこちらの方を振り向いたのが、ひろしにも気配でわかった。
「わ、わかったよ。にいちゃんがそう言うなら、好きなだけ見ていいよ。ただしだ。もし見落としがあって事故にでもなったら、ただじゃおかないからな。これからマチ子と花筐公園に紅葉を見に行くところなんだから」
「あ、ありがとうございます」ひろしは思わず頭を下げた。
「今トランクから車椅子出すから、ちょっと待ってな。マチ子を車から降ろすから」男はそう言うと、車の後ろに回って行った
「お兄さん、ごめんなさいね。この人相変わらず口が悪くて」マチ子さんが優しく言った。
「いえいえ。紅葉がり楽しみですね」
「ええ、ありがとう」
今日あたり花筐公園の紅葉は、ちょうど見頃になっているだろう。
「点検入りまーす」ひろしは、入店以来一番ではないかと思えるような大きな声で叫んだ。すぐさま「点検入りまーす」「入りまーす」というこれも元気な復唱の声が、スタンド内に響き渡る。その声に押されるように、ひろしはゆっくりとピットに向かって歩み始めた。
(了)