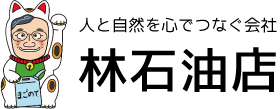「林石油店と5人のお客さま」第4回 まごのて

秋の長雨である。客足は鈍い。
その日の午後、ガソリンスタンドの店先にひろしは立っていた。
「今日はまだ月曜かあ」と少しぼうっとした気分で前の県道を通る車を眺めていると、恵の呼び声が店内から聞こえてきた。
「ひろし君、ちょっと」
「はい」
そろそろ早番だった恵が上がる時間である。引き継ぎ事項でもあるのかと、ひろしは足早に入り口のドアに向かった。
「ひろし君、ちょっと領家まで行ってきてくれないか」
「いいですけど、何でしょう?」
「ふくまの駐在さんから今、電話があって、迷子の柴犬を預かってるって」
「え、もしかして、あの犬ですか?」
「いや、まだわからない。でも柴犬の雑種で赤い首輪をつけているっていうから、きっと間違いないやろ」と言いながら、店内の壁に貼ってある迷い犬のチラシをトントンと指差した。
ちょうど先週末の金曜日のことである。
今日のような小雨模様の中、ひろしが店番をしていると、黒い傘をさした一人の老婆がオロオロとGSのエントランスに現れた。この近所の人ではない。少し長い距離を歩いてきたと見えて、丸まった背中が雨で濡れていた。
「あんちゃん、ちょっと聞いてもいいけの」
「どうしましたか?」
「小次郎、見んかったか?」
「えっ、こ、小次郎ですか?」
「うちの小次郎、来んかったかって」
「こんにちはー、おばちゃん。どうしたの?」戸惑っているひろしの後ろから、ベテラン定員の三崎さんが声をかけた。「まあ、雨降ってるしい、中に入んねの。どうぞ」
三崎さんは慣れた様子で老婆をお店の中に招き入れた。
「おばちゃん、どっから来たの? え? 粟田部? で、小次郎って言うのは、犬? 猫? それともインコかな?」タオルで老婆の背中や服を拭きながら、三崎さんはゆっくりとした口調で話しかけた。
「うちの犬やがの」
「ああ、犬の小次郎君ね。いつからいなくなったの?」
「今朝、餌をやろうとして犬小屋見たら、ひもが外れてて、もう見えんかったんやわの。雨の中どこ行ったんやろ?」
「それは心配やね」
「小次郎君の色は? 茶色? 柴犬かなあ」
三崎さんは、初対面の老婆から、犬の特徴やら連絡先等を次々と聞き出していく。その手際良さに感心するばかりで、ひろしはそのそばに立ち尽くしていた。そして30分後には、「迷い犬」のチラシが店内の情報コーナーに張り出されていた。

「おばちゃん、なんかわかったらまた電話するで。今日は雨やし、もう帰んねの。わかった?」
「死んだ爺さんが、『小次郎、小次郎』って可愛がってたさけ」
「大丈夫や、おばちゃん。今朝いなくなったんなら、まだそんな遠くには行ってえんわの。首輪もついてるし」
「ほうけ。ありがとの」
老婆は店を後にして、再び小雨の降る県道を南に向かって帰って行った。その背中は、どこか寂しげだった。
「見つかるといいですけど」とひろしが言うと、
「見つかるわよ。うちをどこだと思ってるの? 林石油店よ」
三崎さんは、すぐさま満面の笑顔を返してきた。
ここ林石油店は、フルサービスのスタンドとして、給油をはじめオイル・タイヤ交換、洗車、車の点検などはもちろんお手の物だ。その他にも地元のお客さまの悩みを解決するべく、「まごのて事業」というサービスも行っている。林石油店は「かゆいところに手が届く まごのて」になるというというのが、店長のなおきさんのモットーだ。
なので、こうした探し物の相談なども結構寄せられているわけである。その中でも最近のペットブームのせいか、こうしたペット探しに関する情報が増えてきている。
その時の老婆が探しているという犬の情報が、お客さんのネットワークで広がって、今日、隣の地区の駐在さんが「飼い主不明の雑種の柴犬を預かっている」とわざわざ店まで知らせてきてくれたのだ。
「ひろし君、雨で悪いけど頼むわ。社長もちょうど灯油の配達に行ってていないし」新米のひろしにも、いつも優しく接してくれる恵である。
「でも恵さん、今日はもう上がりじゃ」
「私のことはいいから」
「そうですか。すみません」
「ひろし君、君が謝ることじゃないって。第一この雨やろ。どうせこのあと買い物に行くパチンコでも行くくらいしか予定ないから」メガネの曇りを拭きながら、恵はちょっとはにかんだように笑った。
「わかりました。行ってきます」
出かけようとして勢いよくドアを出たひろしは、そこでふと立ち止まって、恵の方を振り返った。

店の右手奥の洗車機の前に、横腹に「まごのて屋」の文字が書かれた軽バンが停まっている。カラフルな色合いで、なんと従業員全員の似顔絵付き。しかもそれはなんと招き猫の格好をしていて、上げた左手が「まごのて」になっている。
「恵さん、《まごのて屋》の車、乗ってっていいですか?」
「何やひろし君、珍しいな。いつもあの車に乗るのは恥ずかしいって言ってるのに」
恵の言うとおり、ひろしはこの車に乗るのが苦手だった。いくら社長の発想とは言え、自分の似顔絵の書かれた車で狭い田舎街を走るのだ。口の悪い同級生仲間に見られたら、何を言われるかわかったものじゃない。
ただし、今日は違っていた。一刻も早く犬を引き取って来て、あのお婆さんの家に届けたい。その時に一番ふさわしいのは、何と言ってもこの《まごのて屋》の車に違いない。
「いや、今日はこれで行かせてください。恵さん、行ってきまーす!」
「お、気いつけてな」
店の前に見える行司ケ岳の中腹あたりには、まだ白いもやがかかっている。しかし、その上の西の空には、わずかに青空も見え始めている。雨が上がるのも近いだろう。
「さあ、頼むぞ」車に乗り込んだひろしは、《まごのて屋》号のハンドルをぽんぽんと軽く叩いた後、エンジンキーを持った右手に力を込めた。
(続く)