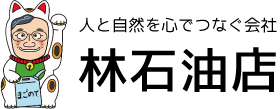「林石油店と5人のお客さま」第3回 野岡小町

異常気象と言えるくらい暑かった今年の夏も、ようやく峠を越したらしい。
その日も日中は暑さが残っていたが、新米店員のひろしが客待ちでガソリンスタンドの店先に立つ夕方頃には、吹き抜ける風は幾分涼しさを伴っていた。
「えー、なおきちゃん、いないのー?」
その時、お店の中からよく通る女性の声が響いてきた。
「そうなんです。週末から代休と休暇をとって、奥様と出雲大社にお参りに行ってまして」ひろしのすぐ上の先輩店員である恵が答えている。「来週月曜までには帰って来るらしいんですけど」
「そんなあ」
甘えたような女性の声が続く。その声の主は、少し前にお店に来た近所の主婦で、「玲ちゃん」とか「玲子さん」という名前で通っている女性である。なかなかの美女で、このあたりでは知らぬ人はいない。
なんでも社長とは小学校以来の同級生とのこと。そうであれば60歳は過ぎている。しかし、ひろしの目には40代後半の自分の母親より若いように見える。この人の車に初めて給油をして「ありがとう」と笑顔で言われた時、ひろしは思わずお釣りの小銭を落としてしまったくらいだ。
「あらあら、どうしちゃったの」そういうときも玲子さんは、にこやかに微笑んで、一緒に小銭を拾ってくれた。ひろしはそれ以来、彼女の隠れファンだ。
いつか、この店で一番古株の女性店員である三崎さんがひろしに言ったことがある。「玲ちゃんは若い頃からこのあたりの地名を採って、『野岡小町』って言われてたのよ。で、これは内緒だけど、社長も若い時分は、玲ちゃんにゾッコンだったらしいわ」
その玲子さんが、今、社長がいないので困っているというのである。店先に立ったままで店内の会話に聞き耳を立てていると、どうやらこういうことらしい。
この林石油店は見かけは普通のGSなのだが、その実は「油も売っている石油店」を標榜していて、驚くほど多様な商品を扱っている。その中でも最も変わった売り物の一つが「土鍋」である。
お店の奥まった部分に土鍋コーナーがあって、大小様々な土鍋が置かれている。伊賀焼の老舗の陶器店と交渉し、直接、商品を仕入れさせてもらっている。
林石油店はプロパンガスの設置販売も行っていて、「ガスでご飯を炊くと美味しいから」というのが、社長の弁。「打倒!電気炊飯器」がモットーだ。
しかも、数年前から「土鍋部・朝練」と称して、土鍋でご飯を炊くミニセミナーまで始める始末である。

「炊飯用土鍋を使いガスでご飯を炊いてみましょう。8月1日から末まで。日曜日はのぞく。毎日朝6時から30分の土鍋でご飯を炊いてみる《朝練》をします。一日一組限定。前日夕方までに、お米のみ持参くださっても構いません。下準備はこちらにてします。炊き上がりから、むらし時間が20分かかりますから そのままお持ち帰りください。ご家族で土鍋朝ご飯を食べてください」とお店が出しているチラシ「店主のささやき」にはある。
最初の頃は、「社長のもの好き」と思われていたが、これがなかなか好評で、結構な比率でお店にはお米や土鍋が持ち込まれている。
それで今日、玲子さんも土鍋を持ってお店に来たのだが、肝心の社長が旅行でいないというものだから、その慌てぶりも理解できるというものだ。
「明日の土曜日、お墓まいりで親戚が集まるので、せっかくだから土鍋でご飯を炊いて、ちらし寿司でも振舞おうかかということになったの。せっかく重い5合炊きの土鍋を持ってここまで持って来たのに」
「それは、大変でしたね」
「どうしましょう。困ったわあ」
その時である。突然、大きな声で自分の名前を叫ぶ恵先輩の声が飛んで来た。
「ちょっと、ひろし君。こっち来て!」
「は、はい」ひろしが急いで店内に走っていくと、続けて彼女が意外なことを言い出した。
「大丈夫ですよ、玲子さん。私たちでなんとかしますよ」
「え、本当?」
「店長がやっている《朝練》を、結構毎日見てますから。それに社長はメモ魔なんで、この《ネタ帳》に「土鍋でお米を炊く方法」がちゃんと書いてあるんです。任せてください」そう言いながら、恵は右手に持った社長愛用のB5のリングノートを自慢げに見せ、ひろしの方を見た。「ねえ、ひろし君」
ひろしの返事を聞くまでもなく、すでに玲子さんの顔は満面の笑みに変わっていた。
「ありがとう。恵さん、ひろしくん。じゃあ、明日朝また来るわ」
玲子さんが上機嫌で帰った後、閉店の準備をしながらひろしが言った。
「恵先輩、土鍋でお米炊いたことあるんですか?」
「いや、ないけど」恵はあっさりと答えた。
「それなのに、さっきはあんな風に安請け合いして・・・大丈夫なんですか?」
「でも、社長がいつも言ってるでしょう。『お客さまからの問い合わせには、<聞いてません><知りません>て言わないこと』って」
「でも本当にご飯炊けるんですか?」
「できない理由はあとにしてくれない。ひろし君、あなたは玲子さんが、なぜみんなに『野岡小町』って呼ばれて慕われているか知ってる?」
「いえ」
「それはあの笑顔よ。もちろんあの人だって、気が滅入ることはあると思うの。でもいつだって口角を上げて、明るい笑顔を見せているでしょ? それが周りの人まで明るくしているのよ」
「・・・」
「明日、あなたは玲子さんの笑顔を見たくないの?」
「いや、そんなことはないけど」
「じゃあ、今からご飯炊きの練習よ」
恵にそう言われると、自分の中になんだかやる気のようなものが湧いてくるのがひろしにもわかった。
こうしてその日の夜、閉店後の店内で恵とひろしの「土鍋部・朝練」ならぬ「土鍋部・夜練」が始まった。
社長のメモをもとに、試行錯誤が何回か繰り返された。
「あー、これじゃ焦げすぎー」
「今度はお米が柔らかすぎて、ちらし寿司には無理ね」・・・
そして日付が変わりかけた頃、ようやくひろしが叫んだ。
「恵先輩!今度はいい感じですよ」

立ち上がってタオルで汗を拭ったひろしは、明日見ることになるだろう玲子さんの笑顔を思い浮かべた。その笑顔はきっと最高の笑顔だろう。すると、これまでの疲れがすっと引いて、自分の顔にも自然に笑みが浮かんでくるのを、ひろしははっきりと感じていた。
「そうね。お米もふっくらしていて、ちょうどいいわ」
(続く)